先日、Kayano blogさんが《バレエ・メカニック》(1924)を紹介していました。
どんな作品なのか、みなさんにも共有します。
この映像を見て「なるほど!」とスッと理解できた方は、もしかすると今日の記事は読まなくても大丈夫かもしれません(笑)。
じつはこの作品は、1920年代という時代にあった「機械化あこがれ」を理解しないとなんのことだか分かりません。そしてこの「機械化あこがれ」は現代にもつながる問題なので、解説していきたいと思います。
2. 《バレエ・メカニック》ってどんな作品?
《バレエ・メカニック》は、1924年にフランスで制作された実験映画です。画家フェルナン・レジェと映画監督ダドリー・マーフィーが共同で手がけ、音楽にはアメリカの作曲家ジョージ・アンタイルが参加しました。断片化された人々の映像と機械、そして抽象的なリズムで構成されています。
画面に現れるのは、ミキサーや歯車、回転する扇風機、そして唇や目といった人間のパーツ。それらが規則的に、あるいは不規則に動きながら、まるで踊っているように展開していきます。それが《バレエ・メカニック》(機械仕掛けのバレエ)というタイトルの理由です。

「バレエ」という言葉に引っかかって、バレエ好きの人がこの映像を見ると面食らうことになる。ダンサーが出てきて踊るわけでもないし、はっきりいってバレエと直接の関係はない。
3. 時代背景:「狂騒の20年代」と機械の進化
この短編映像が作られた1920年代のフランスがどんな時代だったかというと、「狂騒の20年代(Les Années Folles)」と呼ばれる文化的な黄金期でした。
その直前には、第一次世界大戦(1914〜1918)があり、戦車、飛行機、潜水艦といった機械兵器が初めて本格的に戦場に登場します。そこで人々は機械が生み出す巨大な力を目の当たりにしたわけです。
一方、戦後のフランスは復興とともに工業化が進みました。1921年から1929年にかけて、フランスの工業生産指数は約2倍に増加します。戦後の荒廃から、少しずつ人々の生活は豊かになっていきます。
このような背景のなか、文化の面でも華やかな時代が到来します。ジャズやアール・デコが花開き、パリの夜には新しいリズムと光が満ちていました。
なかでも、バレエ・リュスの存在はとりわけ重要です。セルゲイ・ディアギレフ率いるこの舞踊団は、クラシックバレエの形式にとどまらず、美術、音楽、舞台装置を巻き込んだ総合芸術としてのバレエを展開しました。ピカソやマティスといった美術家たちが舞台美術を手がけ、ストラヴィンスキーが音楽を担当するなど、その革新性は群を抜いていました。
機械的な動きや構成美への関心が高まる中で、バレエ・リュスの試みは、まさに舞台上における“モダニズムの実験場”でした。次の章で紹介するレジェやデュシャンといった前衛芸術家たちも、こうした潮流の中で、それぞれの視点から作品を残していきます。
とはいえ、すべての人が機械化を歓迎していたわけではありません。便利で美しい機械に心を躍らせる人々がいた一方で、機械によって労働が単純化され、人間らしさが失われていくことに不安を感じていた人たちもいました。
4. 同時代の三つの作品から見えてくるもの
▸ フェルナン・レジェ《バレエ・メカニック》(1924)
レジェは機械化に対して、非常に前向きな立場をとっていました。彼にとって、機械は人間の生活を豊かにし、リズムや美しさの源でもあったのです。作品の中では、歯車や調理器具などがまるでダンサーのように動き出し、無機物と生命のあいだに境界がなくなっていきます。
▸ フリッツ・ラング《メトロポリス》(1927)
監督のフリッツ・ラングは機械化に対して、否定的な立場をとっていたと言えます。ドイツで制作されたこの映画は、機械化社会に対する警鐘のような内容です。巨大都市の地下では労働者が歯車のように働かされ、上層階級だけが豊かさを享受しています。人間性の喪失、貧富の拡大と階級対立、人間の制御を超えたテクノロジーの恐怖——「未来」が必ずしもバラ色ではないというメッセージが読み取れます。
▸ マルセル・デュシャン《回転する半球体》(1925)ほか
デュシャンは、レジェやラングとはちょっと違った立ち位置です。
彼はキュビスム、ダダイズム、シュルレアリスムといった前衛運動に関わりつつも、一つの流派にとらわれず、モダニズムが持つ人間中心的な考え方そのものへの疑問を投げかけてきました。
「回転する半球体」は、機械仕掛けの回転板を使った目の錯覚というメカニズムを利用しており、「人間の見る世界って本当に信用できるの?」という問いを投げかけます。
また、伝統的な「人の手」による制作ではなく、科学的な原理や視覚効果を利用して、芸術そのもののあり方を問い直し、自身の感情や主観を極力排除しました。
こうしたデュシャンの一連の態度が、彼がポスト・モダンの旗手と言われる所以です。

《回転する半球体》の翌年に制作した、同作の映像版《Anemic Cinema》を紹介するよ。
5. まとめ:機械化とどう向き合うか
このように同じ時代に生きながらも、機械化に対するアプローチは三者三様です。
レジェは希望を、ラングは警鐘を、デュシャンは問いを提示しました。
そして今、僕たちはAIという“新しい機械”と向き合う時代に生きています。便利で美しいものに囲まれながらも、それが人間の感性や労働、判断をどこまで置き換えていくのか、不安もまた拭いきれません。
今はまた、AIを肯定する人、否定する人、そして問いを提示する人たちがいます。
フリッツ・ラングが《メトロポリス》で描いた、巨大なテクノロジーが制御不能に陥る時代は来年、つまり2026年です。
AIの知能が人間を超え予測不可能な技術革新が起きる転換点を「シンギュラリティ」と呼びます。
「シンギュラリティ」が逃げられない運命だとしたら、僕たちはどんな態度で、この瞬間を迎えるべきでしょうか?
1920年代の芸術家たちの視線は、100年を経た今、私たち自身の未来を問い直すヒントになるのかもしれません。

本日よりスタジオアルマが参加するかんだ文化芸術プロジェクト、舞踊劇「食ってきな!-神田食味連着奇譚・蕎麦の巻-」のクラウドファンディングが始まります!
神田の老舗料理店とコラボした素敵なリターンが満載!
本物の老舗蕎麦屋店内で行う特別公演の特別席チケットもあります。
クラウドファンディングの期限は5月31日まで。
皆様のあたたかいご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
詳しくはコチラまで。
最後までお読みいただき、有難うございます!
ブログは毎週火曜・金曜日、音声配信の「ライムライトのつぶやき」は
水曜・土曜日の朝7時に更新しています。
Xをフォロー、もしくはfacebookで「いいね」を押して頂けると、
ブログを更新したタイミングでX(旧Twitter)からお知らせします。
皆さんからのご意見・ご感想もお待ちしています。


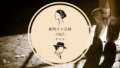
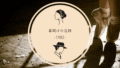
コメント