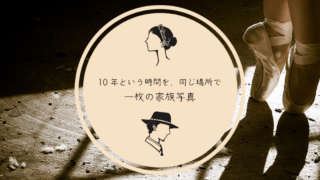 ライムライトの仕事部屋
ライムライトの仕事部屋 10年という時間を、同じ場所で|一枚の家族写真
結婚10年の節目に、10年前と同じ場所で家族写真を撮りました。金沢・兼六園で振り返る、記録と記憶が重なる10年の時間を辿ります。
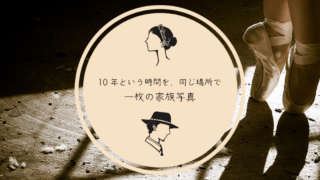 ライムライトの仕事部屋
ライムライトの仕事部屋  ライムライトの仕事部屋
ライムライトの仕事部屋 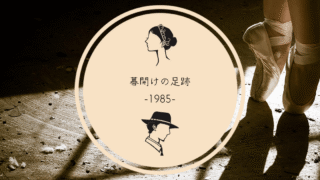 ライムライトの図書館
ライムライトの図書館 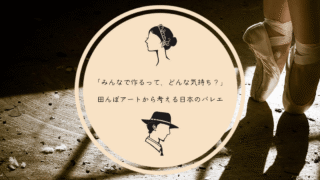 ライムライトの図書館
ライムライトの図書館 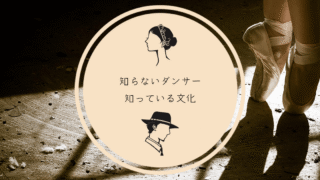 ライムライトの仕事部屋
ライムライトの仕事部屋 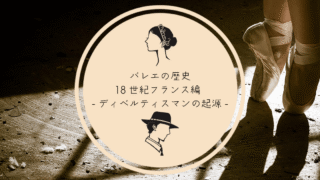 ライムライトの図書館
ライムライトの図書館 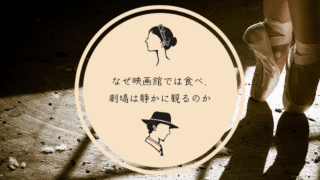 ライムライトの仕事部屋
ライムライトの仕事部屋  ライムライトの仕事部屋
ライムライトの仕事部屋  ライムライトの図書館
ライムライトの図書館 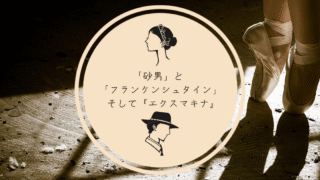 ライムライトの図書館
ライムライトの図書館