8月の執行バレエスクール発表会で上演される《コッペリア》。過去記事でもこの作品はすでに紹介していますが、この愛らしいバレエ作品の原作が、実はドイツ・ロマン主義文学の巨匠E.T.A.ホフマン*の怪奇小説「砂男」であることをご存知でしょうか。
*後期ロマン派を代表する幻想文学のドイツの作家であり、作曲家、音楽評論家、画家、法律家。
今日は、なぜ怪奇小説がバレエの傑作に生まれ変わったのか、そして現代の僕たちがこの作品から読み取るべきものについて考えてみたいと思います。
ロマン主義が生んだ「不気味な人形」
ホフマンが「砂男」を執筆したのは1816年。これはドイツ・ロマン主義文学の全盛期にあたります。
ロマン主義とは、18世紀末から19世紀にかけてヨーロッパを席巻した芸術運動です。理性や合理性を重視した啓蒙主義への反動として生まれ、恋愛、想像力、そして神秘的なものや異世界への憧れを特徴としていました。ゲーテの「若きウェルテルの悩み」やベートーヴェンの交響曲群、そしてバレエ《コッペリア》もロマン主義時代の産物です。
ホフマンは、このロマン主義の中でも特に「幻想文学」の分野で才能を発揮しました。現実と幻想の境界線を曖昧にし、読者を不安に陥れる手法は、後の怪奇小説やSF小説の原型となっています。
以下が「砂男」のあらすじです。
幼い頃、父の死に関わったとされる謎の男「砂男」(コッペリウス)に怯えていた大学生ナタナエル。彼はやがて、コッポラと名を変えた砂男と再会する。彼は砂男から購入した望遠鏡で向かいに住む自動人形オリンピアを覗きこみ、徐々に魅せられていく。婚約者のクララがいるにも関わらずず、人形にのめり込むナタナエルは、やがてオリンピアが人形であると発覚すると狂気に陥る。最後は、発狂したまま塔から身を投げて死に至る。

この作品でホフマンが描いたのは、思い込みや恐怖に駆られた人間が、現実とファンタジーの区別を失っていく様子です。人間らしく見えるものが実は人工物だったという、人間の実存性に対する危うさ、自信のなさが現れています。
バレエが選んだ「光」の解釈
1870年にパリ・オペラ座で初演されたバレエ《コッペリア》は、振付師アルテュール・サン=レオンと台本作家シャルル・ニュイッテルによって、ホフマンの原作を大胆にアレンジされました。最も大きな変更点は、物語のトーンを恐怖から喜劇へと転換したことです。
この劇的な変化の背景には、1817年の「砂男」発表から1870年のバレエ初演までの約半世紀にわたる社会変化があります。ホフマンの時代は、ナポレオン戦争後の政治的混乱期で、フランスとドイツの間の国境線は確定せず、ロマン主義が隆盛を極め、人々は内面世界の闇や幻想、人間の深層心理に潜む狂気への関心を抱いていました。理性では説明できない超自然的なものへの畏怖が、文学作品に求められていたのです。

この時代のドイツはどちらかというと「不安定で暗い」時代。日本で言うとバブルが崩壊した90年代の雰囲気が近いかも。長引く不況下でオウム真理教の地下鉄サリン事件や阪神淡路大震災があり、「エヴァンゲリオン」が大ヒットして、人々の意識が内側に向かっていた時代。
しかし、1870年代に入ると、普仏戦争経てドイツはドイツ帝国として統一され、産業革命が本格化し、都市化が進み、中産階級が台頭していました。社会はより合理的で物質的な発展を追求する時代となっていました。人々が求めるのは、もはや内省的な恐怖ではなく、日常の労働から離れた明るく健全な娯楽だったのです。
バレエ《コッペリア》の制作陣は、こうした時代の要請に応えて、原作の怪奇性を排して、より「人間の温かみ」や「本物の愛」の価値を前面に押し出すことを選んだのだと思います。
スワニルダ(主人公の少女)が人形に成りすまして老博士を翻弄するという設定も、この時代ならではの発想です。「本物の人間が人形の真似をする」ことで、逆に人間の生き生きとした魅力を際立たせる構造は、近代化が進む社会において人間性の価値を再確認させる、楽観的なメッセージとなっています。
AI時代の私たちが見る「コッペリア」
さて、ここで現代の話です。
ChatGPTをはじめとするAIが人間のような文章を書き、人間のような会話をする時代になりました。
まさに、ホフマンが描いた「人間と人工物の境界線の曖昧さ」を、内面世界の出来事ではなく、僕たちはリアルに体験しているのです。
ここで注目すべきは、原作「砂男」に登場する二人の人物の対照的な反応です。ナタナエルの親友ジークムントは、オリンピアに対して最初から不気味さを感じ取っていました。一方、ナタナエルは強い思い込みによって、人形に対する「不気味の谷」を乗り越えてしまったのです。
「不気味の谷」とは、1970年にロボット工学者の森政弘氏が提唱した考え方で、ロボットが人間に近づくにつれて親しみやすさが増すものの、ある段階で急激に不気味さや嫌悪感を抱くようになる現象です。しかし興味深いことに、さらに人間に近似してくると、再び愛着や親近感を抱くようになるとされています。つまり、人間らしさの度合いに対する好感度は、途中で深い谷を描くU字カーブになるのです。
ナタナエルは恋愛感情という強いバイアスによって、この不気味の谷を一気に飛び越え、オリンピアを完全に人間として受け入れてしまいました。
現代でも、フェイクニュースや偽情報、ディープフェイクといった問題において、技術そのものの精度よりも、受け取る人間側の認知バイアス、つまり「見たいものを見る」という心理的傾向の方が、より深刻な問題を引き起こす場合があります。ナタナエルのように、僕たちは自分の願望や先入観によって、AIの作り出す虚実を正しく判断できなくなる危険性を常に抱えています。
ホフマンが200年前に予見していたのは、技術の進歩が人間のアイデンティティを脅かす時代だけでなく、人間の認知の偏りこそが最大のリスクとなる時代だったのかもしれません。
まとめ
今、日本の90年代を振り返って見ると、「意外と内省できる余裕のある、呑気な時代だったな。」と感じてしまいます。
あれから僕たちは、東日本大震災やコロナ禍など、人間世界の外側にある自然の猛威に晒されて、人間中心主義の限界を知ってしまいました。また、AIの急速な発展は、もう一つの人ならざる自然「デジタルネイチャー」として、人がAIにどう打ち勝つのかではなく、どのように共存していくかが問われている時代です。
「砂男」が描かれたロマン主義全盛の時代、《コッペリア》が上演された人間中心の時代、そして現代。
8月の発表会で《コッペリア》をご覧になる際は、ぜひこうした背景も思い出していただければと思います。舞台上で踊る生身の人間たちが表現する「人形と人間の物語」には、200年の時を経て僕たちの時代にも通じる深いメッセージが込められています。
AIが台頭する時代だからこそ、人間が人間として踊ることの意味を、改めて舞台から受け取っていただければと思います。
最後までお読みいただき、有難うございます!
ブログは毎週火曜・金曜日、音声配信の「ライムライトのつぶやき」は
水曜・土曜日の朝7時に更新しています。
Xをフォロー、もしくはfacebookで「いいね」を押して頂けると、
ブログを更新したタイミングでX(旧Twitter)からお知らせします。
皆さんからのご意見・ご感想もお待ちしています。


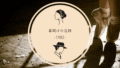
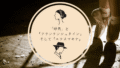
コメント