しばらくブログの更新が空いてしまいました。8月は執行バレエスクールの発表会やスタジオアルマの公演、映像の仕事、そして子どもの夏休みが重なり、文章に向かう時間がほとんど取れませんでした。
少し落ち着いたので、今日は「カタカナとしてのクラシックバレエ」について、外からの目線で考えてみたいと思います。
カタカナとしてのクラシックバレエとは?
日本で「クラシックバレエ」と聞くと、チュチュ姿の踊り子や『白鳥の湖』『眠れる森の美女』といった華やかな舞台を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。一方、フランスや英語圏では単に “ballet” と呼ばれています。
では、なぜ日本では「クラシック」という言葉をわざわざ付けているのでしょうか。
これは戦後、「モダンバレエ」や「現代舞踊」との区別として使われるようになったことが背景にあるのではないかと思います。
そう考えると、「クラシックバレエ」という呼称そのものが、日本独自の翻訳文化の一端を示しているように思います。

ただし、「モダンバレエ」という表現自体、日本でモダンダンスとバレエを融合した表現を指す言葉として使われていて、いつ頃から用語として広まったのかについては明確ではないんだ。モダンバレエという言葉の成り立ちについては、僕の音声配信の方で詳しく話しているよ。
個人教室が支えてきた日本のクラシックバレエと国立バレエ団の誕生
日本のバレエ界は、圧倒的多数が個人経営の教室を基盤に広がってきました。地域ごとに先生がいて、生徒がいて、そこから舞台が育まれる。この草の根的な広がりは裾野を広げる力を持っていますが、同時に教室ごとに技術水準の差が生じやすい面もあります。
僕の祖父・執行正俊は、その点を問題視していました。生前から「日本には国立のバレエ団が必要だ」と訴えていたのです。そして祖父の死後、1997年に新国立劇場バレエ団が誕生し、その理想は徐々に現実のものとなりました。
ただ、祖父が生きていた時代から現在に至るまで日本のバレエは「中央集権的な仕組み」ではなく、「周縁の集合体」として成り立っているように思います。ここに、ヨーロッパの国立学校や国立バレエ団を中心に育成が体系化されてきた仕組みとの違いがあるのではないでしょうか。
プロとアマチュアが共演する、日本独自のクラシックバレエ発表会文化
日本のバレエを語るときに欠かせないのが「発表会文化」です。多くの教室では一年から二年に一度、ホールを借りて大規模な発表会を行います。照明や衣裳も本格的で、まるでプロ公演のように仕上げられることが少なくありません。
一方で、欧米の多くの教室では、発表会は「リサイタル」と呼ばれ、比較的小規模に行われることが多いようです。スタジオの中や地域の小さな劇場で、生徒たちだけが登場し、練習の成果を披露する形が一般的です。もちろん本格的な舞台を用意することもありますが、日本ほど徹底してプロ公演に近づける例は少ないように思います。
さらに特徴的なのは、日本ではアマチュアとプロが同じ舞台に立つことです。執行バレエスクールでも、これまで国内外からプロのダンサーを招き、生徒と共演する形で発表会を続けてきました。リハーサルで子どもたちがプロの動きを食い入るように見つめ、本番で同じ照明を浴びながら踊る。そうした経験は、生徒にとって大きな「憧れ」を育む場になっていると思います。
観客の多くは保護者や関係者に限られますが、外国人の保護者から見れば「子どもがプロのダンサーと同じステージ上で共演できる」ということは大きな驚きであり、誇りでもあるのではないでしょうか。そう考えると、発表会文化は閉じた場でありながら、外から見ればユニークな文化資源として価値を持ちうると思います。
プリンシパル中心ではない? 発表会が示す新しいバレエの形
国内外を問わず、バレエ団の世界では、プリンシパル、ソリスト、アーティストといったヒエラルキーが明確に存在します。大規模な舞台ではその構造が不可欠なのかもしれません。
けれども、日本のバレエ教室の発表会文化を見ていると、そこには別の可能性が潜んでいるように思います。
発表会は文字通り生徒が日頃の努力の成果を発表することが前提ですから、「参加者全員が輝く瞬間を作ること」が前提になっています。ですから、ピラミッド型のヒエラルキーを前提としない新しい構成が自然に生まれる土壌があります。
とくに生徒数が少ない教室であれば、群舞的な動きもソリスト的な見せ場も、同じ生徒がどちらも踊る構成が出てくると思います。

複数人で構成されているアイドルグループを思い浮かべて欲しい。アイドル一人一人の見せ場もあるし、全員で踊るパートもある。
これは教育的な配慮にとどまらず、今後のバレエ表現にヒントを与えるものかもしれません。従来の序列を超えて、多様性を前提とした舞台のあり方を考える――そんな可能性を、発表会文化は静かに示しているように思います。
日本のクラシックバレエ観客層は“プレーヤー”が中心?
もう一つ、日本のバレエを特徴づけているのは観客層のあり方です。ヨーロッパでは、バレエはオペラや演劇と同じように一般市民が日常的に楽しむ芸術です。観客は必ずしも踊った経験を持たず、文化として鑑賞に親しんでいます。
一方で日本では、観客の多くが教室の関係者やかつて習った経験のある「プレーヤー層」だと思います。その背景には、公演数の構造そのものがあります。
文化庁委託の『バレエ教育に関する全国調査2021』によれば、日本のバレエ教室は全国で約4,260件存在し、そのうち約87%が発表会を開催しています。つまり年間に換算すると、少なくとも1,800回、多ければ3,700回規模の発表会が全国で行われていることになります。
これに対して、プロのバレエ団による公演は全国合計でも数百回規模にとどまります。数字だけを見ても、日本では「発表会を観に行く」経験の方が圧倒的に一般的なのです。
発表会の観客は、生徒の家族や友人といった関係者が中心です。そのため、日本で「バレエを観る」という行為は、まず誰か身近な人を応援しに行く経験として根付いてきました。そうした観客体験の積み重ねが、プロの公演に足を運ぶ人々の多くもまたバレエ経験者や関係者である、という状況につながっているのではないでしょうか。
この構造は、バレエ人口が減少すると観客人口も同時に減るという課題を抱えています。けれども同時に、観客自身が舞台の意味を深く理解し、身近に感じているという強みでもあると思います。
閉じているからこそ成立する「濃密な観客文化」――これは日本ならではの特徴ではないでしょうか。
オタク文化や秘祭に通じる、日本のバレエ文化の閉じた構造
このような「閉じた文化」から独自性が生まれるのは、日本文化全般に通じる特徴のように思います。
アニメオタクカルチャーやアイドル文化は、かつては内輪のものとされていましたが、やがて海外から注目される文化資源になりました。さらに遡れば、地域の秘祭や民俗芸能もまた、閉じた共同体が守ってきたからこそ残ってきたと言えるのではないでしょうか。
心理学者の河合隼雄は、日本文化を「中空構造」と呼びました。中央に権威的な核を持つのではなく、小さな共同体が無数に存在し、全体を形づくるという考え方です。日本の「クラシックバレエ」も、国立バレエ団を持ちながら、実態としては教室や発表会といった小さな円環が集まり、全体を形づくっているように思います。
まとめ
日本のクラシックバレエは、閉じたコミュニティの中で独自の形を育んできました。観客層が狭く、発表会中心という構造は課題でもありますが、その濃密さは外から見れば独自の魅力になるのではないでしょうか。
たとえば、一流のプロダンサーと子どもが同じ舞台に立つ経験や、アマチュアでも本格的な舞台を作り上げる熱心さ、観客自身が踊りの経験があるという、出演者と観客の濃密な関係性――こうした点は、海外から見ればきっと新鮮でユニークに映るのだと思います。
僕自身、バレエ教室の家に育ち、その空気を知りながらダンサーにはならず、外の視点を持つ立場として、この「カタカナのクラシックバレエ」を言葉にしていくことに意義を感じています。
このブログに書くことは、閉じた文化を外に開く小さな試みでもあります。課題を抱えつつも独自の形を築いてきた日本のクラシックバレエ。
その姿をどう未来に生かせるのか――今後も問いかけていきたいと思います。
最後までお読みいただき、有難うございます!
ブログは毎週火曜・金曜日、音声配信の「ライムライトのつぶやき」は
水曜・土曜日の朝7時に更新しています。
Xをフォロー、もしくはfacebookで「いいね」を押して頂けると、
ブログを更新したタイミングでX(旧Twitter)からお知らせします。
皆さんからのご意見・ご感想もお待ちしています。


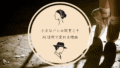
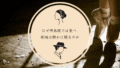
コメント