 ライムライトの図書館
ライムライトの図書館 幕開けの足跡 -1967- その3
今日は、1967年の第22回芸術祭に祖父が作品を出品したプログラムから、日本の西洋舞踊史における重要人物のひとり、高田せい子氏と祖父とのエピソードをご紹介します。
 ライムライトの図書館
ライムライトの図書館 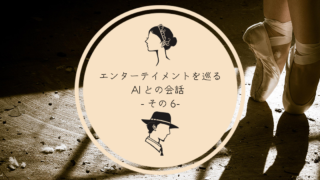 ライムライトの図書館
ライムライトの図書館  ライムライトの図書館
ライムライトの図書館  ライムライトの図書館
ライムライトの図書館 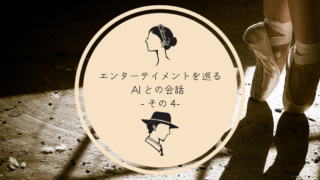 ライムライトの図書館
ライムライトの図書館 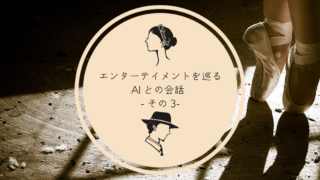 ライムライトの図書館
ライムライトの図書館 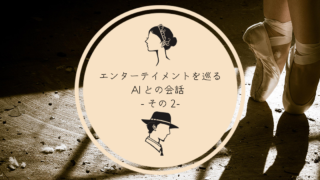 ライムライトの図書館
ライムライトの図書館 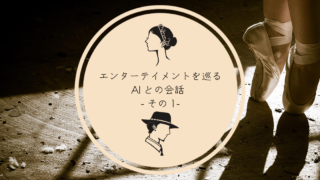 ライムライトの図書館
ライムライトの図書館  ライムライトの図書館
ライムライトの図書館 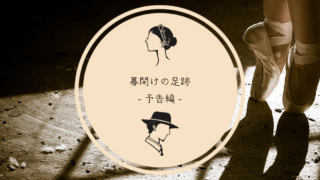 ライムライトの図書館
ライムライトの図書館