先日の音声配信で、田んぼアートについて話しました。
青森県の田舎館村で始まった村おこしのアート。色の違う稲を植え分けて、高台から見ると一枚の絵になる。平面性、ドット絵、アノニマス性——すごく日本的だなと思いました。
音声配信では、この田んぼアートとバンクシーのストリートアートを比較しました。どちらも「消えることが前提」のアートだけど、バンクシーが抵抗の象徴なら、田んぼアートは共生の象徴。対立ではなく、包摂する。
音声配信で話してみて、改めて考えました。

掬茶 – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25681625による
これって、日本のバレエにも通じるんじゃないか?
今日は、田んぼアートから考える、日本のバレエの可能性について書いてみたいと思います。
田んぼアートとバンクシー -共生と対立-
まず、音声配信で話した僕が「日本的だ」と感じた田んぼアートの特徴を簡単にまとめます。
- 平面性
- 田んぼアートの魅力は、何と言っても平面性です。田んぼの前に立ってもただの田んぼにしか見えないけど、視点を変えると巨大な絵が現れる。平面の中に世界を作るのは、浮世絵や掛軸、アニメーションにも通じる、日本の得意技です。
- ドット絵
- ファミリーコンピューターのゲーム『マリオブラザーズ』のマリオは、今やドット絵として世界的な認知を得ています。稲の種類を使い分けて、最初は3色、今は7色。ゲームボーイ以上、ファミコン以下の色数で、モナリザや『鬼滅の刃』を表現する、田んぼアートはドット絵でもあります。
- アノニマス性
- 特定の作者がいない、農家の人やボランティアがみんなで作る民芸。『鬼滅の刃』も、原作者や監督の名前ではなく、制作チーム全体の力で話題になった作品です。

ここで重要なのは田んぼを上から見た時に絵が見えるようにするには、しっかりとした遠近法の測量が必要だということ。「鬼滅の刃」が立体的な3D空間で平面キャラをアニメーションさせるように、西洋から学んだ技法を積極的に取り込んでオリジナルにしちゃうところも日本的。
そして音声配信の後半は、田んぼアートとバンクシーを比較してみました。
バンクシーのストリートアートは、違法に街の壁に描かれ、やがて誰かの手で消される。その消えることが作品の一部。これは西洋芸術が神に捧げる永続性を追求してきたことへの、カウンターでもあります。
一方で、田んぼアートも消えることが前提。田植えをして、夏に絵が現れて、秋には収穫して消える。でもこれは対立ではありません。人と自然が協力して、季節の循環の中で生まれて消えていく。町おこしでやってるから、当然、町も反対していません。
同じ消えることを前提としたアートでも、バンクシーは抵抗の象徴、田んぼアートは共生の象徴。
この対比から、僕は身体表現における「対立」と「包摂」について考え始めました。
西洋で生まれたバレエの上昇志向
クラシックバレエの特徴を一言で表すなら、上昇志向です。
つま先立ちで、できるだけ高く、できるだけ軽やかに。重力に逆らって天に向かう。これは西洋芸術が神に捧げるものとして発展してきた歴史と無関係ではありません。
バレエの起源は、16世紀のフランス宮廷にあります。イタリアから持ち込まれた舞踏が、フランスで洗練されて「バレエ」になった。そして19世紀のロマンティック・バレエで、白いチュチュを着た妖精や幽霊が登場するようになります。
『ラ・シルフィード』や『ジゼル』に代表されるロマンティック・バレエは、地上の人間と異界の存在との恋を描きます。手の届かない理想、この世のものではない美しさ。そしてポワント(つま先立ち)の技術が確立されて、ダンサーたちは文字通り地面から浮き上がろうとします。
この上昇志向は、西洋の大聖堂の尖塔や、ゴシック建築の垂直性とも共通しています。地上から天へ、人間から神へ。永遠なるものへの憧憬。
そして西洋芸術のもう一つの特徴が永続性です。
石で作られた彫刻、油絵の技法、楽譜に記された音楽。できるだけ長く、できるだけ完璧な形で後世に残そうとする。神に捧げるものだから、永遠でなければならない。
バレエも同じです。振付は記録され、継承され、何百年も前の作品が今も踊られている。クラシックバレエの代名詞である『白鳥の湖』は1877年の初演から150年近く経った今も、世界中で上演されています。

150年を「古い」と感じるか「新しい」と感じるかは人によると思うけど、いわゆる *3大バレエは、繰り返し上演される「殿堂入り」作品として、「クラシック」の名前を冠しても良いと思う。
*プティパ振付、チャイコフスキー作曲による『白鳥の湖』、『眠れる森の美女』、『くるみ割り人形』の3作品のこと
日本で生まれた舞踏の下降志向
ここで、バレエとは正反対の身体性を持つ「舞踏」の話をします。
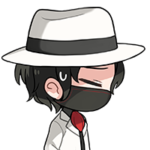
といっても、僕はバレエ以上に舞踏は詳しくない上に、「舞踏」に関する定義は未だ確立していないので、あくまで一般論として受け取ってね。
舞踏とは、1960年代に日本で生まれた身体表現のジャンルです。土方巽や大野一雄といった舞踏家たちが創始し、「死」を連想させるようなその踊りは「暗黒舞踏」とも呼ばれました。
舞踏の身体性は、バレエとはまったく逆を向いています。
全身を白く塗り、低く構え、重心を落とし、地を這うように動く。つま先立ちで上昇するのではなく、膝を曲げて地面に沈み込む。軽やかさではなく、重さ。天ではなく、土。
日本の身体性は、もともと低重心です。武道でも農作業でも、腰を落として地面に近いところに重心を置く。能や歌舞伎の所作も、すり足で地面との接地を意識する。
そして日本人は、死や土、腐敗といったものを忌避せず、むしろそこに美を見出してきました。

お花見や花火は、「消えゆくもの」を愛でる風習として僕たちにとっても身近なものだよね。
舞踏家たちが表現したのは、この下降する身体でした。神への憧憬ではなく、生と死の循環。美しく完成された形ではなく、変容し続ける身体。永続性ではなく、刹那性。
そして舞踏の源流には、20世紀初頭にヨーロッパで生まれたモダンダンスがあります。僕の祖父・執行正俊がドイツで学んだノイエタンツも、このモダンダンスの一つでした。祖父と同じマリー・ウィグマン舞踊学校で学んだ江口隆哉というダンサーが日本でモダンダンスを広め、その江口に師事したのが大野一雄や土方巽だったのです。
モダンダンスがバレエに対するカウンターとして生まれたように、舞踏は、戦後日本において西洋のバレエへのカウンターとして生まれました。上昇する身体ではなく、下降する身体。軽やかさではなく、重さと土の記憶。
これ、バンクシーに似てませんか? 西洋芸術の永続性へのカウンターとしてストリートアートが生まれたように、舞踏は西洋バレエへのカウンターとして生まれた。どちらも「対立」「抵抗」の芸術です。
祖父の試み——対立ではなく融合へ
さて、ここで話を僕の祖父に戻します。
祖父・執行正俊は、ドイツでノイエタンツを学んで帰国しました。戦前は同盟国のドイツからもたらされたモダンダンスのムーブメントの真っ只中です。
しかし戦後、大きな価値転換が起こります。
敗戦を機に戦前の文化は忌避され、日本全体ではヨーロッパの戦勝国やアメリカの文化の流入とともに、クラシックバレエが急速に普及していったのです。
松山バレエ団(1948年)、谷桃子バレエ団(1949年)、牧阿佐美バレエ団(1956年)——戦後すぐから、民間主導でバレエ団が次々と設立されていきます。
そのような状況下で、祖父が選んだのは、どちらも捨てない、という道でした。
クラシックバレエの作品も振り付けながら、モダンダンスの要素を加えた「モダンバレエ」の探究も進めていった。「幕開けの足跡」シリーズで紹介しているように、祖父は発表会でクラシック作品とオリジナル作品の両方を上演し続けました。
《ファウスト》や《オルフェ》といったオリジナル作品には、ドイツで学んだノイエタンツの要素が色濃く残っています。一方で、クラシックバレエの技法も教え、古典作品も振り付けています。
これは、舞踏が選んだ道とは違います。
バンクシーが体制への抵抗を貫くように、舞踏は、バレエへのカウンターとして、徹底的に対立する道を選びました。
しかし祖父は、対立ではなく融合を目指した。
バレエの上昇志向とモダンダンスの身体性、どちらも価値があると考えた。西洋から来た技法と、日本人の身体感覚、どちらも大切にしたかった。

これって、田んぼアートの発想に近くない?
現代日本のバレエ——包摂する身体表現
もうひとつ、別の観点から日本のバレエシーンを見ていきます。
民間主導で広がった「日本のバレエ」
日本には約4,300のバレエ教室があって、推定25万人がバレエを習っています。世界でも有数の「バレエ大国」です。
しかし、日本のバレエの広がり方は独特でした。国立劇場ができたのは1997年と遅く、それまでは完全に民間主導。各地の教室が、それぞれの場所で、自分たちの手でバレエを育ててきました。
そして日本では、バレエが女性の習い事として定着しました。ヨーロッパでは職業としてのバレエが中心ですが、日本では「バレエを習う」ことそのものが文化になった。
強力な個人だったり国の主導ではなく、草の根的に「習い事」として広まった日本のバレエ文化はアノニマスな民藝として田んぼアートに接続します。

みんなで田植えをして、夏に絵を見て、秋に収穫するっていう、田んぼアートはまるでバレエの発表会みたい。プロになるかは別として、バレエを踊る喜びを共有する場所。
まとめ
ここまで、日本文化の「包摂性」について書いてきましたが、教室文化を基盤とした日本のバレエが、今後包摂すべきものは何でしょう?
現在のヨーロッパのバレエは、クラシックとコンテンポラリーの両方を取り入れた訓練を行っています。一方、日本ではそのような取り組みが普及しているとは言えません。

じゃあ、日本もコンテンポラリーの訓練方法を導入すれば良いんじゃない?
そんな単純な話ではないと思います。そんなことはこれまでも散々言われてきた上で、今の日本のバレエ文化があるのですから。
僕が問いたいのは「何を教えるか」ではありません。
コンテンポラリーの源流を追求すれば、それは決まった型を真似することではなく、踊り手自身の内面を行為に結びつけることです。祖父が学んだノイエタンツも、舞踏が追求したのも、個人の内面を身体で表現することでした。
コンテンポラリーの本質って、「型」じゃなくて「考え方」なんじゃないか?
ならば、教室ができることは「何かを教える」ことではなく、「共に考え、気付く(=築く)」ことではないでしょうか。
それは、踊ることに負けず劣らず、一朝一夕で手に入ることではありませんが、そんな視点で教室という環境を考えてみるのも良いかもしれません。
個人的には、来年、息子と一緒に行田市の田んぼアートの田植えに行こうと思っています。そして一緒に田植えをして、夏に絵を見て、秋に収穫したお米を食べる。
そして息子に聞いてみます。
「みんなで作るって、どんな気持ち?」
もしかしたら、その答えが日本のバレエの未来につながっているかもしれません。
最後までお読みいただき、有難うございます!
ブログは不定期、音声配信の「ライムライトのつぶやき」は
毎週日曜日の朝7時に更新しています。
Xをフォロー、もしくはfacebookで「いいね」を押して頂けると、
ブログを更新したタイミングでX(旧Twitter)からお知らせします。
皆さんからのご意見・ご感想もお待ちしています。

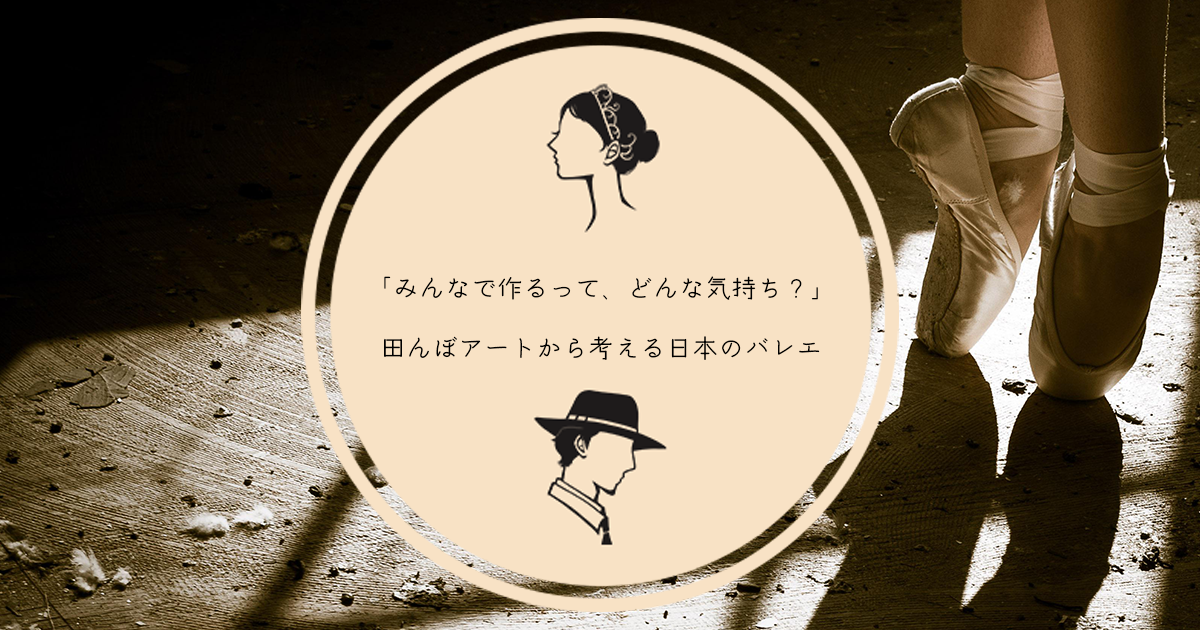
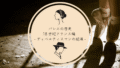
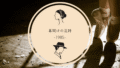
コメント