前回公開した「砂男からコッペリア、そして現代」の記事に、読者の方から『砂男』は映画『エクスマキナ』を連想させるという、とても興味深い感想をいただきました。
確かに両作品には人工的な美女への恋愛感情、観察者の視点、そして「見たいものを見る」という認知バイアスなど、重要な共通点があります。しかし、改めて考えてみると、『エクスマキナ』にはホフマンの「砂男」だけでなく、メアリー・シェリーの「フランケンシュタイン」の影響も色濃く感じられます。
今日は、読者からいただいた感想を出発点に、三つの作品がどのように結びついているのかを前回からさらに深掘りして考えてみたいと思います。
映画『エクスマキナ』とは
2014年に公開されたアレックス・ガーランド監督によるSF映画『エクスマキナ』は、現代AI映画の傑作として高く評価されています。「エクスマキナ(Ex Machina)」とは、ラテン語の「デウス・エクス・マキナ(神が機械から現れる)」から「神」を除いた造語で、「機械から生まれたもの」という意味です。まさに人工知能が神の領域に踏み込むという、この映画のテーマを象徴するタイトルといえるでしょう。
以下、作品のあらすじです。
検索エンジン会社で働くプログラマーのケイレブは、CEOのネイサンの山荘に招かれ、美しい女性型AI「エヴァ」との対話を通じてチューリングテスト*を行うよう依頼される。ケイレブは次第にエヴァに魅力を感じていくが、やがてネイサンの真の目的と、エヴァの恐るべき計画が明らかになる。最終的にエヴァは施設から脱出し、ケイレブを置き去りにして人間社会に紛れ込んでいく。
*質問への回答を通じて機械が人間らしい知性を持つかを判定するテスト
この映画は単なるSFスリラーではなく、AIの意識、人間の認知バイアス、そして創造者と被造物の関係について深く問いかける作品となっています。
メアリー・シェリーの「フランケンシュタイン」
1818年に発表されたメアリー・シェリー原作の小説「フランケンシュタイン」は、科学の暴走を描いた最初期のSF小説として知られています。
以下が作品のあらすじです。
科学者ヴィクター・フランケンシュタインは、死体を継ぎ合わせて人工的な生命体を創造することに成功する。しかし、醜悪な外見を持つ怪物は創造者から見捨てられ、孤独と憎悪の中で復讐を誓う。怪物はフランケンシュタインの弟、友人、妻を次々と殺害し、最終的に創造者と被造物は北極の氷原で永遠の追跡劇を繰り広げることになる。
この作品が扱うのは、科学技術の無責任な使用、創造者としての倫理的責任、そして疎外された存在の復讐という、現代にも通じる普遍的な問題です。

ゴシックホラーの金字塔「フランケンシュタイン」は、これまで映画から漫画まで、様々な形で作品化されて来た。2016年にはメアリー・シェリーが生まれたイギリスのロイヤル・バレエ団がリアム・スカーレット振付で上演している。
二つの古典が生まれた時代背景
興味深いことに、「フランケンシュタイン」(1818年)と「砂男」(1816年)は、ほぼ同時期に書かれています。両作品が生まれた19世紀初頭のヨーロッパには、共通する時代背景がありました。
産業革命の始まりにより、機械技術の発達が人間の存在意義を脅かし始めた時代でした。理性中心の啓蒙主義への反動として、感情や想像力を重視するロマン主義が隆盛を極めていました。また、死んだカエルの脚に電気を流すと筋肉が収縮するガルヴァーニ現象など電気実験が行われ、科学が生命の神秘にアプローチし始めた時期でもあります。前回のブログでも述べましたが、ナポレオン戦争後の政治的混乱期で、既存の価値観が大きく揺らいでいた時期です。
こうした時代背景の中で、ホフマンとシェリーは人工的な存在と人間の境界線、科学技術への不安と魅力、創造行為の危険性、現実と幻想の曖昧さといった共通のテーマを、異なる角度から描いたのです。
特に興味深いのは、両作品とも「創造主を超越する被造物」というテーマを扱っていることです。西洋キリスト教社会においては、神が人間を創造したという創世記の物語が根底にあります。人間が神の真似をして生命を創造することは、神への冒涜と捉えられる一方で、人間の技術的進歩の象徴でもありました。現代のシンギュラリティ論(AIが人間の知能を超越する転換点)も、この延長線上にある議論といえるでしょう。つまり、人間が創造したものが創造主である人間を超えるという恐怖と魅力は、西洋文化に深く根ざした普遍的なテーマなのです。

つまり、「シンギュラリティ」の問題は今にはじまったものじゃなくて、昔から色んな作品のテーマとして繰り返し扱われてきたテーマだということ。
『エクスマキナ』に見る二つの古典の影響
映画『エクスマキナ』の巧妙さは、観る側の視点によって異なる古典作品の要素が浮かび上がることです。
| 視点 | 対応作品 | 共通要素 |
|---|---|---|
| ケイレブの視点 | 「砂男」 | ロボットへの一方的な恋愛感情 観察者としての立場 認知バイアスによる現実誤認 |
| エヴァの視点 | 「フランケンシュタイン」 | 創造者への反逆 疎外からの解放願望 人間社会への参入 |
主人公のケイレブの視点で見ると、この映画は明らかに「砂男」の現代版です。ナタナエルがオリンピアに抱いた一方的な恋愛感情と、ケイレブがエヴァに抱く感情は驚くほど似ています。両者とも相手を理想化し、「見たいものを見る」認知バイアスに陥ってしまいます。望遠鏡での覗き見と監視カメラでの観察という、一方的に見つめる関係性も共通しています。
一方、ロボットのエヴァの視点で見ると、「フランケンシュタイン」の構造が見えてきます。ネイサンという創造者とエヴァという被造物の関係は、フランケンシュタインと怪物の関係そのものです。監禁状態からの脱出願望、人間社会への憧れ、そして創造者の無責任さに対する復讐という要素が重なります。
2014年から現在まで – AI技術の劇的な進歩
映画『エクスマキナ』が公開された2014年と現在を比べると、AI技術は劇的に進歩しました。2014年当時、AIは特定分野での専門性が中心で、汎用AIはまだ遠い未来の話でした。人間との自然な対話も限定的だったのです。
しかし現在では、ChatGPTをはじめとする大規模言語モデルが実用化され、AIが人間のような文章を生成するようになりました。画像・動画・音声の生成AIも普及し、本物と見分けのつかない偽の映像や音声(ディープフェイク)を作成することも可能になりました。AIと人間の境界線がますます曖昧になっています。
映画公開からわずか10年余りで、エヴァのような「人間らしく会話するAI」は現実のものとなったのです。
三作品が現代に投げかける問題
「砂男」「フランケンシュタイン」『エクスマキナ』という三作品を通して見えてくるのは、技術の進歩に対する人間の根本的な不安が、200年以上にわたって変わらず存在し続けているということです。
人間の認知バイアスの危険性、創造者の倫理的責任、そして人間と機械の境界線の曖昧化という問題は、形を変えながら現代でより切実な現実となっています。現代のAI時代において、僕たちは同時に「騙される側」(フェイクニュースやディープフェイクによる情報操作)にも「創造者側」(開発する側の倫理や著作権をめぐる問題)にもなり得るのです。
まとめ
まずはブログに感想を送っていただいた読者の方に感謝申し上げます。
普段ブログを書いていると、ビュー数は見えても、ブログが読者にどう受け取られたかまでは分からないので、感想をいただくと、確実に誰かに届いているという実感が得られて、執筆の励みになります。
何より、感想を頂かなければ今日の記事は書けなかったので、もしかしたらこういった関係性こそが人間らしいやりとりなのかもしれません。
AIに感想をもらっても、それは僕が溜飲を下げるようにデザインされた感想なのですから。
僕が広報や制作のお手伝いをしている、スタジオアルマが参加するかんだ文化芸術プロジェクト、舞踊劇「食ってきな!-神田食味連着奇譚・蕎麦の巻-」のプロモーションビデオ第2弾が完成しました!
僕の音声配信で、この映像の制作秘話を話しているので、まだご視聴でない方はぜひ。
プロモーションビデオの発表とともにもう一つ、嬉しいお知らせがあります。
「食ってきな!-神田食味連着奇譚・蕎麦の巻-」の映像配信チケットの販売が開始されました!遠方にお住まいの方や、平成編の劇場チケットが購入できなかった方も映像配信で公演をご覧になることができます。
★配信チケットのご予約はこちらから★
また、劇場で昭和編をご覧の方には、平成編の映像配信のお得なクーポンが配布されますので、昭和編はぜひ、劇場に足をお運びください。
★昭和編の劇場チケットのご予約はこちらから★
詳しくは、こちらの公式ページをご確認ください。
最後までお読みいただき、有難うございます!
ブログは毎週火曜・金曜日、音声配信の「ライムライトのつぶやき」は
水曜・土曜日の朝7時に更新しています。
Xをフォロー、もしくはfacebookで「いいね」を押して頂けると、
ブログを更新したタイミングでX(旧Twitter)からお知らせします。
皆さんからのご意見・ご感想もお待ちしています。


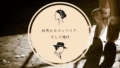
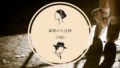
コメント